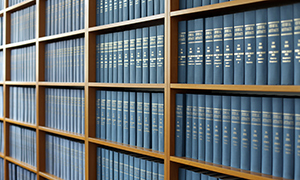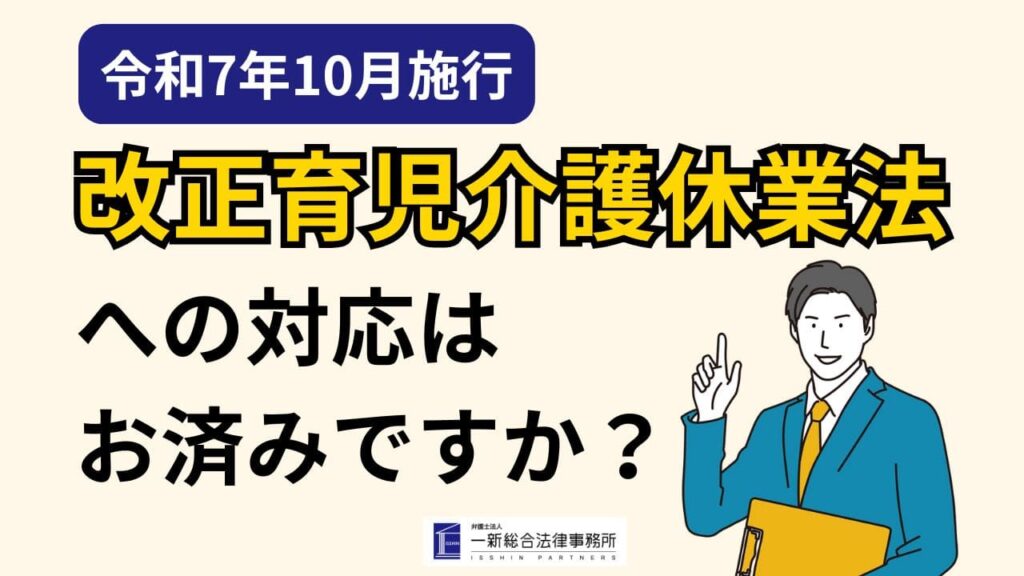2025/07/17
法務情報
令和7年10月施行 改正育児介護休業法への対応はお済みですか?(弁護士:五十嵐 亮)
■育児期の働き方を見直す法改正──令和7年10月施行の新たな対応義務
近年、育児と就労の両立支援は、少子化対策の一環としても重要視されるようになってきました。
育児休業の取得促進や男性の育児参加の強化など、制度面の整備が段階的に進められてきましたが、令和7年10月からは、より実務に即した柔軟な働き方への対応が求められることになります。
今回の法改正の柱は大きく二つです。
一つは「3歳から小学校就学前までの子を育てる労働者に対する柔軟な働き方制度の整備義務」、もう一つは「妊娠・出産から3歳到達前までの段階での個別の意向聴取と配慮義務」です。
■背景:制度はあるが利用しにくいという現実
これまで、育児休業や短時間勤務制度など、育児期の労働者を支援する制度は一定程度整備されてきましたが、実際には「制度があっても使いにくい」「利用にあたって職場との調整が難しい」といった声も多く、制度の実効性には課題がありました。
特に、子が3歳を過ぎてから小学校入学までのいわゆる「育児中期」においては、保育園・幼稚園との調整、行事参加、体調不良への対応など、引き続き育児負担は大きいにもかかわらず、制度面での支援が手薄でした。
こうした状況を受け、今回の改正では、企業に対して柔軟な働き方の選択肢を用意する義務が新たに課されることとなりました。
■柔軟な働き方制度の導入義務
3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対し、企業は以下の5つの支援措置のうち少なくとも2つ以上を導入することが求められます。
- 始業・終業時刻の変更(時差出勤やフレックスタイム制等)
- テレワーク(月10日以上を目安とする)
- 保育施設の設置・運営支援やベビーシッター利用支援
- 年10日以上の「養育両立支援休暇」の制度
- 所定労働時間を短縮する「短時間勤務制度」
これらの制度は、導入すればよいというものではなく、過半数労働組合等から意見を聴取したうえで制度設計を行う必要があります。
また、労働者は事業主が導入した制度のうち1つを選んで利用することができます。
企業にとっては制度導入に加えて運用体制の整備も課題となりますが、長期的には人材の定着や労働力の確保という観点からも、制度活用を促進することの意義は大きいといえます。
■個別周知・意向確認の義務
育児期の働き方を実効あるものにするには、制度が存在することを労働者が認識し、安心して申請できる環境を整えることが重要です。
そのため、今回の改正では、3歳未満の子を育てる労働者に対して、子が3歳になる前の適切な時期に、以下の事項について個別に周知・意向確認を行うことが義務づけられます。
・柔軟な働き方に関する制度の内容
・利用申出の手続き
・時間外労働・深夜業等の制限に関する制度の内容
・本人の制度利用に関する意向
周知と確認は、面談・書面・オンライン面談・メール等の方法により行うことが可能です。
加えて、事業主には本人の意思を尊重し、不利益な取扱いがなされないよう留意する義務も生じます。
■妊娠・出産段階からの意向聴取と配慮
もう一つの改正点として、妊娠・出産の段階から、企業が労働者の勤務に関する意向を確認し、それに応じた配慮を行うことが新たに義務化されます。
具体的には、妊娠・出産の申出があった際と、子が3歳になる前の一定時期に、以下の事項について本人の希望を聴取し、必要に応じて業務内容や就業場所、勤務時間の調整などに配慮することが求められます。
・勤務時間帯や所定労働時間の希望
・就業場所(在宅勤務や配属先など)
・両立支援制度の利用期間に関する希望
・業務内容や量の調整に関する希望
このように、今回の法改正は「本人のニーズを把握したうえでの対応」を強く打ち出しています。
配慮の実施にあたっては、業務運営とのバランスも考慮されますが、可能な限り柔軟な対応が求められる点には注意が必要です。
■制度から実践へ──運用次第で効果に差
今回の改正は、単に制度を整えるだけでなく、「利用される制度」にするための働きかけと運用の仕組みを企業側に求める内容となっています。
これまで課題とされてきた「制度があっても使えない」「育児中に働きづらい」といった実態を改善することが狙いとなります。
ただし、これらの制度は企業にとって新たな負担となる面もあるため、社内の制度設計やマニュアル整備、管理職への教育など、段階的な準備が不可欠です。
制度の内容を従業員に正しく伝え、利用をためらわせない職場づくりが、今後の重要なポイントとなるでしょう。
育児と就労の両立をめぐる環境は、法制度の整備を通じて徐々に改善が進められています。
今回の改正も、企業にとっては一つの転換点となります。
制度を形だけにせず、現場に根づかせていく取り組みが今後求められていきます。
【ご注意】
◆記事の内容については、執筆当時の法令及び情報に基づく一般論であり、個別具体的な事情によっては、異なる結論になる可能性もございます。ご相談や法律的な判断については、個別に相談ください。
◆当事務所は、本サイト上で提供している情報に関していかなる保証もするものではありません。本サイトの利用によって何らかの損害が発生した場合でも、当事務所は一切の責任を負いません。
◆本サイト上に記載されている情報やURLは予告なしに変更、削除することがあります。情報の変更および削除によって何らかの損害が発生したとしても、当事務所は一切責任を負いません。
カテゴリー
月間アーカイブ
- 2026年1月(2)
- 2025年12月(1)
- 2025年11月(2)
- 2025年10月(1)
- 2025年9月(2)
- 2025年8月(2)
- 2025年7月(2)
- 2025年6月(3)
- 2025年5月(1)
- 2025年4月(2)
- 2025年3月(1)
- 2025年2月(2)
- 2025年1月(2)
- 2024年12月(2)
- 2024年11月(2)
- 2024年10月(1)
- 2024年9月(1)
- 2024年8月(1)
- 2024年7月(2)
- 2024年6月(2)
- 2024年5月(2)
- 2024年4月(1)
- 2024年3月(2)
- 2024年2月(2)
- 2024年1月(1)
- 2023年12月(1)
- 2023年10月(2)
- 2023年9月(2)
- 2023年8月(2)
- 2023年7月(2)
- 2023年5月(1)
- 2023年4月(2)
- 2023年3月(2)
- 2023年2月(2)
- 2023年1月(2)
- 2022年12月(3)
- 2022年11月(2)
- 2022年10月(1)
- 2022年9月(1)
- 2022年8月(2)
- 2022年7月(2)
- 2022年6月(1)
- 2022年5月(1)
- 2022年4月(1)
- 2022年3月(2)
- 2022年2月(1)
- 2022年1月(1)
- 2021年12月(1)
- 2021年11月(1)
- 2021年10月(2)
- 2021年9月(2)
- 2021年6月(1)
- 2021年4月(2)
- 2021年3月(1)
- 2021年1月(3)
- 2020年12月(3)
- 2020年11月(10)
- 2020年10月(5)
- 2020年9月(7)
- 2020年8月(4)
- 2020年7月(3)
- 2020年6月(3)
- 2020年5月(11)
- 2020年4月(5)
- 2020年3月(2)
- 2019年12月(1)
- 2019年9月(1)
- 2019年7月(2)
- 2019年6月(3)
- 2019年5月(2)
- 2019年4月(1)
- 2019年3月(3)
- 2019年2月(2)
- 2018年12月(1)
- 2018年10月(2)
- 2018年9月(1)
- 2018年7月(1)
- 2018年6月(1)
- 2018年5月(1)
- 2018年4月(1)
- 2018年3月(1)
- 2017年12月(1)
- 2017年11月(2)
- 2017年5月(1)
- 2017年3月(1)
- 2017年2月(2)
- 2016年12月(5)
- 2016年8月(2)
- 2016年7月(3)
- 2016年5月(1)
- 2016年4月(2)
- 2016年3月(4)
- 2016年2月(3)
- 2016年1月(1)
- 2015年11月(1)
- 2015年9月(1)
- 2015年8月(1)
- 2015年7月(1)
- 2015年6月(1)
- 2015年4月(1)
- 2015年3月(2)
- 2015年1月(3)
- 2014年9月(6)
- 2014年8月(3)
- 2014年6月(3)
- 2014年5月(3)
- 2014年4月(2)
- 2014年2月(2)
- 2014年1月(2)
- 2013年12月(5)
- 2013年11月(1)
- 2013年10月(5)
- 2013年9月(5)
- 2013年8月(2)
- 2013年7月(2)
- 2013年6月(4)
- 2013年5月(2)
- 2013年4月(3)
- 2013年3月(3)
- 2013年2月(2)
- 2013年1月(1)
- 2012年12月(2)
- 2012年11月(2)
- 2012年10月(1)
- 2012年9月(2)
- 2012年8月(2)
- 2012年7月(2)
- 2012年6月(2)
- 2012年5月(1)
- 2012年4月(2)
- 2012年2月(2)
- 2012年1月(3)
- 2011年12月(2)
- 2011年11月(3)
- 2011年10月(3)
- 2011年9月(8)
- 2011年8月(10)
- 2011年7月(8)
- 2011年6月(8)
- 2011年5月(10)
- 2011年4月(9)
- 2011年3月(9)