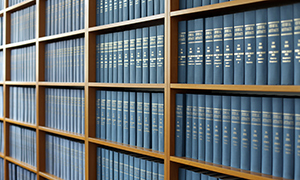2022/11/07
法務情報
自筆証書遺言書保管制度とは~メリットとデメリット
コラム、遺言・相続・後見、新潟事務所、長岡事務所、上越事務所、燕三条事務所
1 はじめに
法務局で自筆証書遺言書保管制度が開始してから2年以上が経過しました。
法務省の発表によれば、令和4年9月までに累計4万1764件の保管申請があったそうです。
今回は、遺言書について解説したいと思います。
2 遺言書をつくるメリット
遺言書がない場合、相続人全員で遺産の分け方を協議します(これを「遺産分割協議」といいます)。
相続人間の関係が良好で、話し合いにより遺産の分け方がスムーズに決められるのであれば、遺言書がなくても特に問題はありません。
しかしながら、
・相続人間の関係が険悪で、協議が出来ない…
・相続人のなかに面識のない人がおり、連絡が取りづらい…
・遺産として不動産しかなく、分け方が決められない…
など協議が難航するケースもあります。
そのような場合、遺言書があれば、基本的にはそれに従い相続人等が遺産を取得しますので、遺産分割協議をする必要がありません。
無用な争いを回避し、スムーズな相続を実現するために、遺言書を作成しておく意味があります。
3 保管制度のメリット
法務局での自筆証書遺言書の保管制度は、上記に加え、
・法務局で遺言書を保管するので、紛失のおそれがない
・相続人等による遺言書の破棄、隠匿、改ざん等を防ぐことが出来る
・相続開始後、家庭裁判所における検認が不要
・相続開始後、相続人等は、法務局において遺言書を閲覧したり、遺言書情報証明書の交付が受けられる
というメリットがあります。
せっかく遺言書を作っても紛失したり、相続人が発見できなければ意味がありません。
保管制度はそのようなリスクを回避できるメリットがあります。
4 自筆証書遺言書のデメリット
法務局の保管制度の対象は、自筆証書遺言です。
自筆証書遺言は、紙と筆記用具と印鑑があれば気軽に作れます。
しかし、自筆証書遺言書を拝見していると、
・書かれていることが曖昧、多義的であるため、遺言の内容が分からない
・預金や不動産がきちんと特定されていないので、誰が、何を取得するのか分からない
など問題がある場合も少なくありません。
また、本人が一人で作るため、後々、判断能力の有無が問題となり、遺言書の有効性が争われるケースもあります。
そのようなリスクを考えると、せっかく作るのであれば、弁護士などの専門家に相談して遺言書を作成することをお勧めします。
ご相談いただければ、ご要望に応じた遺言書の内容や作成方法などをご提案いたします。
*一新総合法律事務所では相続・遺言に関するご相談は初回無料(45分)で承っております。お気軽にお問い合わせください。
◆弁護士コラム一覧はこちら
◆相談のご予約・お問い合わせはこちら
【ご注意】
◆記事の内容については、執筆当時の法令及び情報に基づく一般論であり、個別具体的な事情によっては、異なる結論になる可能性もございます。ご相談や法律的な判断については、個別に相談ください。
◆当事務所は、本サイト上で提供している情報に関していかなる保証もするものではありません。本サイトの利用によって何らかの損害が発生した場合でも、当事務所は一切の責任を負いません。
◆本サイト上に記載されている情報やURLは予告なしに変更、削除することがあります。情報の変更および削除によって何らかの損害が発生したとしても、当事務所は一切責任を負いません。
カテゴリー
月間アーカイブ
- 2026年1月(2)
- 2025年12月(1)
- 2025年11月(2)
- 2025年10月(1)
- 2025年9月(2)
- 2025年8月(2)
- 2025年7月(2)
- 2025年6月(3)
- 2025年5月(1)
- 2025年4月(2)
- 2025年3月(1)
- 2025年2月(2)
- 2025年1月(2)
- 2024年12月(2)
- 2024年11月(2)
- 2024年10月(1)
- 2024年9月(1)
- 2024年8月(1)
- 2024年7月(2)
- 2024年6月(2)
- 2024年5月(2)
- 2024年4月(1)
- 2024年3月(2)
- 2024年2月(2)
- 2024年1月(1)
- 2023年12月(1)
- 2023年10月(2)
- 2023年9月(2)
- 2023年8月(2)
- 2023年7月(2)
- 2023年5月(1)
- 2023年4月(2)
- 2023年3月(2)
- 2023年2月(2)
- 2023年1月(2)
- 2022年12月(3)
- 2022年11月(2)
- 2022年10月(1)
- 2022年9月(1)
- 2022年8月(2)
- 2022年7月(2)
- 2022年6月(1)
- 2022年5月(1)
- 2022年4月(1)
- 2022年3月(2)
- 2022年2月(1)
- 2022年1月(1)
- 2021年12月(1)
- 2021年11月(1)
- 2021年10月(2)
- 2021年9月(2)
- 2021年6月(1)
- 2021年4月(2)
- 2021年3月(1)
- 2021年1月(3)
- 2020年12月(3)
- 2020年11月(10)
- 2020年10月(5)
- 2020年9月(7)
- 2020年8月(4)
- 2020年7月(3)
- 2020年6月(3)
- 2020年5月(11)
- 2020年4月(5)
- 2020年3月(2)
- 2019年12月(1)
- 2019年9月(1)
- 2019年7月(2)
- 2019年6月(3)
- 2019年5月(2)
- 2019年4月(1)
- 2019年3月(3)
- 2019年2月(2)
- 2018年12月(1)
- 2018年10月(2)
- 2018年9月(1)
- 2018年7月(1)
- 2018年6月(1)
- 2018年5月(1)
- 2018年4月(1)
- 2018年3月(1)
- 2017年12月(1)
- 2017年11月(2)
- 2017年5月(1)
- 2017年3月(1)
- 2017年2月(2)
- 2016年12月(5)
- 2016年8月(2)
- 2016年7月(3)
- 2016年5月(1)
- 2016年4月(2)
- 2016年3月(4)
- 2016年2月(3)
- 2016年1月(1)
- 2015年11月(1)
- 2015年9月(1)
- 2015年8月(1)
- 2015年7月(1)
- 2015年6月(1)
- 2015年4月(1)
- 2015年3月(2)
- 2015年1月(3)
- 2014年9月(6)
- 2014年8月(3)
- 2014年6月(3)
- 2014年5月(3)
- 2014年4月(2)
- 2014年2月(2)
- 2014年1月(2)
- 2013年12月(5)
- 2013年11月(1)
- 2013年10月(5)
- 2013年9月(5)
- 2013年8月(2)
- 2013年7月(2)
- 2013年6月(4)
- 2013年5月(2)
- 2013年4月(3)
- 2013年3月(3)
- 2013年2月(2)
- 2013年1月(1)
- 2012年12月(2)
- 2012年11月(2)
- 2012年10月(1)
- 2012年9月(2)
- 2012年8月(2)
- 2012年7月(2)
- 2012年6月(2)
- 2012年5月(1)
- 2012年4月(2)
- 2012年2月(2)
- 2012年1月(3)
- 2011年12月(2)
- 2011年11月(3)
- 2011年10月(3)
- 2011年9月(8)
- 2011年8月(10)
- 2011年7月(8)
- 2011年6月(8)
- 2011年5月(10)
- 2011年4月(9)
- 2011年3月(9)