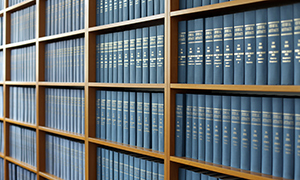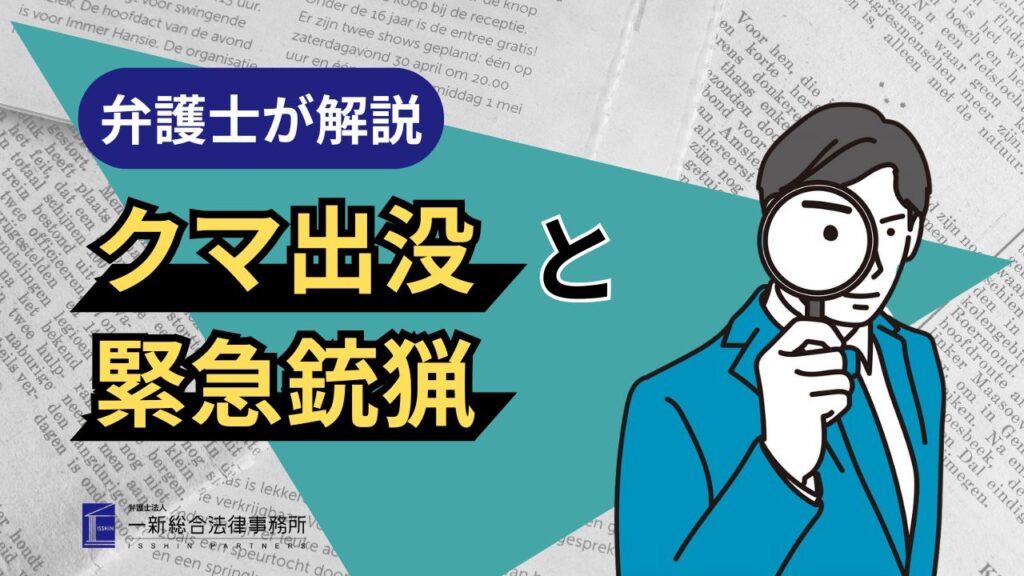2025/11/10
法務情報
クマ出没と緊急銃猟(弁護士:中川 正一)
最近、クマ出没のニュースをよく見かけます。
クマ等が出没した際に、猟友会の方に駆除してもらうニュースなど見かけることが多いですが、クマ等の駆除を巡って法的な問題が発生していますのでご紹介します。
1.行政処分の是非
(1) 事案
ヒグマが出没した際に、市の要請に基づき、猟銃でヒグマを駆除したところ、「弾丸の到達するおそれのある建物に向かって」銃猟したと扱われ、銃刀法違反に基づき、ライフル銃の所持許可を取り消す行政処分がなされました。
(2) 問題の所在
銃刀法は銃などの所持の許可を受けた場合でも原則として発砲を禁止しています。
ただし、有害鳥獣駆除の用途に供するため猟銃等の許可を受けた者が、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下「鳥獣保護管理法」といいます。)の規定により鳥獣の捕獲等をする場合を発砲禁止の例外と定めています(銃刀法10条2項1号)。
ところで、鳥獣保護管理法38条3項では「弾丸の到達するおそれのある人…建物…に向かって、銃猟をしてはならない。」と定めています。
前記事案では、弾丸の到達するおそれのある建物が存在し、それに向かって発砲したと判断されたため、鳥獣保護管理法に違反し、前記銃刀法の発砲禁止の例外とみなされない結果、発砲自体が銃刀法違反と判断されたもので、当該判断の当否が以下の裁判によって争われました。
(3) 行政処分取消請求(第一審)
第一審では、以下の事情を重視しました。
- 被処分者の出動は、市の要請に基づく公益目的であり、警察官及び市職員も赴いていた上、当該職員からの依頼によりヒグマを駆除する決意をしたものであり、警察官もライフル銃の発射の可能性を認識しながらこれを制止することなく、むしろ発射を前提に近くの住民の避難誘導をしていた。
- 発射現場から見える建物は1軒限りで、しかも屋根の一部のみが見える状況であり、わずか15mないし19m程度しか離れていないヒグマに向かって、本件ライフルを構えた後、ヒグマが立ち上がるの待って発射したところ、弾丸はヒグマに逸れることなく命中し、当該弾丸がヒグマの体を貫通し、更に跳弾してどこかへ飛んだような事実は確認されていない。
- 住民Aは本件駆除をしてもらって良かったと述べ、市職員も、今回のようなケースで発砲者が行政処分を受けると住民に不安を与えてしまうと陳述した。
このような事情を総合考慮して、仮に本件発射行為が、鳥獣保護管理法、銃刀法に違反したと判断する余地があるとしても、これを理由とする本件行政処分は、裁量権の範囲を逸脱し又は濫用したものと言わざるを得ない、として行政処分を取り消す判断をしました。
(4) 行政処分取消請求(控訴審)
控訴審では、鳥獣保護管理法38条3項は、弾丸の到達するおそれのある人、建物等に向かってする銃猟行為は、人の生命、身体等に対する危険を防止しつつこれを行うことが困難であることから一律にこれを禁止しており、その行為の当該具体的状況の下における具体的危険の有無を問わないものと判断しました。
そのうえで、被処分者が本件ライフルを向けた方角の90メートル以内に建物が5軒あったことから、本件発射行為は「建物等に向かってする銃猟行為」に該当すると判断し、禁止する鳥獣保護管理法、銃刀法に違反するとしました。
さらに、裁量権の逸脱にあたるかの判断についても、以下の点を重視しました。
- 本件発射行為による弾丸が周辺建物5軒に到達する相応の危険性があったところ、当該違反行為は軽微とはいえない。
- 弾丸の跳飛の一般的様相は極めて複雑で、跳弾は飛んで行く方向が分からず複数回起こりうる等に鑑みると、本件発射行為は現場にいた警察官や市職員の生命・身体も危険にさらしたというべきである。
- 被処分者は、捜査が開始されてから本件処分時までの間に、本件発射行為が危険なものであることを受け入れず、一貫してその正当性を主張しており、同種違反の再発可能性があると言わざるを得ない。
控訴審は、このような評価の下、裁量権の逸脱・濫用に当たらないとしました。
結論としては、第一審の判断を取り消し、行政処分を有効としました。
これは猟友会にとって衝撃的な内容でした。跳弾の予測は難しく、現場を萎縮させるなどの現場も声もあるようです。
2.立法による修正
(1)背景となる課題
近年、クマやイノシシが人の日常生活圏に出没し、人身被害が発生するなど、生活環境の保全上の支障が生じる事例が増加しています。
令和7年2月時点の鳥獣保護管理法は、住居集合地域等における銃猟、人や建物等に向かってする銃猟等を禁止していますが、出没したクマ等が建物に立てこもるなど膠着状態にある場合において、予防的で迅速な対応が求められていました。
このような背景を踏まえ、クマ等の銃猟に関する制度を見直し、人の日常生活圏にクマ等が出没した場合に、地域住民の安全の確保の下で銃猟を可能とすることが思考されました。
(2)法改正の内容と趣旨
具体的には、クマ等が人の日常生活圏に侵入し、クマ等による人の生命又は身体への危害を防止する措置が緊急に必要で、銃猟以外の方法では的確かつ迅速にクマ等の捕獲等をすることが困難であり、非難等によって地域住民に弾丸が到達するおそれがない場合において、市町村長が、クマ等の銃猟を捕獲者に委託して実施させること(緊急銃猟)ができるように法改正し、令和7年9月1日から施行されました。
また緊急銃猟の実施にあたり、「地域住民等の安全確保のため、必要に応じ、市町村長は通行制限、避難指示を実施すること」「市町村長は、都道府県知事に応援を要請できること」「緊急銃猟の実施に伴う損失(物損)については、市町村長が補償(保険による対応を想定)すること」などの関連規定を整備しました。
当該改正法では、緊急銃猟の際には、法38条の適用を除外していますので、建物が密集する人の日常生活圏においても発砲が許されることを想定しており、前記行政処分のような紛争を回避する狙いがあります。
ただし、法38条3項は「建物」等だけでなく「人」に向かって発砲することも禁止しているところ、この部分に限っては、「市町村長の指揮を受け、人の生命又は身体に危害を及ぼすことがないように当該緊急銃猟を実施する場合に限」(法34条の2第5項ただし書)り、適用除外を認めています。
(3)ガイドラインと運用上の留意点
緊急銃猟にはその実施にあたり、ガイドライン(令和7年7月版)が制定されています。
ガイドラインには、「クマ等の出没時には、必ず緊急銃猟をもって対応しなければならないわけではなく、現場の状況を観察されながら、追い払い等を含む複数の手段の中から適切な手段を選択し、クマ等の出没に対応されたい」と記載されており、9月1日の施行後も緊急銃猟の準備をしたが、クマが山に立ち去ったことから実施しなかった例もあります。
3.現状
令和7年10月15日、仙台市において緊急銃猟制度によりクマ1頭を駆除したことが全国初として報じられました。
新潟でも同月21日、魚沼市で全国3例目として緊急銃猟が実施されました。
また、同月31日には、阿賀野市の建設会社にクマが約5時間にわたって留まり、麻酔銃を使った緊急銃猟が全国で初めて実施されました。
(1) 改正法の効果
改正法では法38条3項の適用を排除する緊急銃猟制度を設けて、「建物」が密集する日常生活圏における発砲も適正手続に則れば許されることになり、最初にご紹介したような行政処分のようなことは今後起こらないように配慮されています。
(2) 「人に向かって」の場合
緊急銃猟制度においては、法38条3項の「人」に対しては、「市町村長の指揮を受け、人の生命又は身体に危害を及ぼすことがないように当該緊急銃猟を実施する場合」に限って適用除外を認めています。
つまり、一律適用除外される「建物」の場合と異なり、場合によっては適用除外されないことを想定しています。
また、前記ガイドラインでは、安全を確保するための措置の1つとして「通行禁止・制限範囲の設定」の項目で「射線方向(発射した銃弾に直接被弾するおそれがある範囲)には、通行禁止・制限措置を必ず講じて、屋内外を含め人がいない状態とする。」と定めながら、「一方で、必ずしも捕獲者の前方180°全てに人がいない状態を作らなければならない訳ではない。」(ガイドラインp40)とも記載されています。
この点、前記控訴審では、跳弾の複雑性を根拠に、現場にいた警察官や市職員の生命・身体も危険にさらしたとも判断しています。
そうすると、事後的に裁判で争われれば、跳弾の複雑性を根拠に「人の生命又は身体に危害を及ぼすことがないように当該緊急銃猟を実施する場合」とはいえないと評価され、法38条3項が適用されてしまう場合が全く無いとはいえないと思われます。
このような状況では、発砲者は、事後的に法38条3項の「人に向かって」発砲したと評価され行政処分を受けるリスクから解放されたとはいえず、猟友会の不安も完全に解消されたとはいえません。
(3) 今後
クマ出没が急増し、死亡事件も発生している現状に照らし、猟友会が躊躇なく対応できる体制の確立が期待されます。
特に跳弾による危険性をどのように判断するかは改正前の判断と共通するところ、前記事例の最高裁判断が待たれています。
なお、クマ出没が多い秋田・岩手県においては、機動隊の警察官によるライフル銃でのクマ駆除が11月13日から運用されるようです。
【ご注意】
◆記事の内容については、執筆当時の法令及び情報に基づく一般論であり、個別具体的な事情によっては、異なる結論になる可能性もございます。ご相談や法律的な判断については、個別に相談ください。
◆当事務所は、本サイト上で提供している情報に関していかなる保証もするものではありません。本サイトの利用によって何らかの損害が発生した場合でも、当事務所は一切の責任を負いません。
◆本サイト上に記載されている情報やURLは予告なしに変更、削除することがあります。情報の変更および削除によって何らかの損害が発生したとしても、当事務所は一切責任を負いません。
カテゴリー
月間アーカイブ
- 2025年12月(1)
- 2025年11月(2)
- 2025年10月(1)
- 2025年9月(2)
- 2025年8月(2)
- 2025年7月(2)
- 2025年6月(3)
- 2025年5月(1)
- 2025年4月(2)
- 2025年3月(1)
- 2025年2月(2)
- 2025年1月(2)
- 2024年12月(2)
- 2024年11月(2)
- 2024年10月(1)
- 2024年9月(1)
- 2024年8月(1)
- 2024年7月(2)
- 2024年6月(2)
- 2024年5月(2)
- 2024年4月(1)
- 2024年3月(2)
- 2024年2月(2)
- 2024年1月(1)
- 2023年12月(1)
- 2023年10月(2)
- 2023年9月(2)
- 2023年8月(2)
- 2023年7月(2)
- 2023年5月(1)
- 2023年4月(2)
- 2023年3月(2)
- 2023年2月(2)
- 2023年1月(2)
- 2022年12月(3)
- 2022年11月(2)
- 2022年10月(1)
- 2022年9月(1)
- 2022年8月(2)
- 2022年7月(2)
- 2022年6月(1)
- 2022年5月(1)
- 2022年4月(1)
- 2022年3月(2)
- 2022年2月(1)
- 2022年1月(1)
- 2021年12月(1)
- 2021年11月(1)
- 2021年10月(2)
- 2021年9月(2)
- 2021年6月(1)
- 2021年4月(2)
- 2021年3月(1)
- 2021年1月(3)
- 2020年12月(3)
- 2020年11月(10)
- 2020年10月(5)
- 2020年9月(7)
- 2020年8月(4)
- 2020年7月(3)
- 2020年6月(3)
- 2020年5月(11)
- 2020年4月(5)
- 2020年3月(2)
- 2019年12月(1)
- 2019年9月(1)
- 2019年7月(2)
- 2019年6月(3)
- 2019年5月(2)
- 2019年4月(1)
- 2019年3月(3)
- 2019年2月(2)
- 2018年12月(1)
- 2018年10月(2)
- 2018年9月(1)
- 2018年7月(1)
- 2018年6月(1)
- 2018年5月(1)
- 2018年4月(1)
- 2018年3月(1)
- 2017年12月(1)
- 2017年11月(2)
- 2017年5月(1)
- 2017年3月(1)
- 2017年2月(2)
- 2016年12月(5)
- 2016年8月(2)
- 2016年7月(3)
- 2016年5月(1)
- 2016年4月(2)
- 2016年3月(4)
- 2016年2月(3)
- 2016年1月(1)
- 2015年11月(1)
- 2015年9月(1)
- 2015年8月(1)
- 2015年7月(1)
- 2015年6月(1)
- 2015年4月(1)
- 2015年3月(2)
- 2015年1月(3)
- 2014年9月(6)
- 2014年8月(3)
- 2014年6月(3)
- 2014年5月(3)
- 2014年4月(2)
- 2014年2月(2)
- 2014年1月(2)
- 2013年12月(5)
- 2013年11月(1)
- 2013年10月(5)
- 2013年9月(5)
- 2013年8月(2)
- 2013年7月(2)
- 2013年6月(4)
- 2013年5月(2)
- 2013年4月(3)
- 2013年3月(3)
- 2013年2月(2)
- 2013年1月(1)
- 2012年12月(2)
- 2012年11月(2)
- 2012年10月(1)
- 2012年9月(2)
- 2012年8月(2)
- 2012年7月(2)
- 2012年6月(2)
- 2012年5月(1)
- 2012年4月(2)
- 2012年2月(2)
- 2012年1月(3)
- 2011年12月(2)
- 2011年11月(3)
- 2011年10月(3)
- 2011年9月(8)
- 2011年8月(10)
- 2011年7月(8)
- 2011年6月(8)
- 2011年5月(10)
- 2011年4月(9)
- 2011年3月(9)