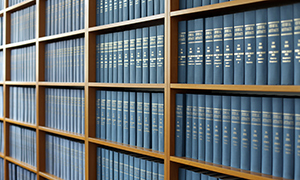2017/12/20
ブログ
2017年、祝日土曜の日数
新潟事務所、燕三条事務所、長岡事務所、新発田事務所、上越事務所、東京事務所
今年も残すところあと10日少々となりました。
天皇誕生日の祝日が12月23日なのも、残りわずかですね。
祝日といえば、今年は祝日が土曜日と被ることが非常に多い1年でした。
すでにみなさまご存じのとおり、祝日が土曜日と被ったとしても、振替休日は発生しません。
これは土日祝日休みの会社員のみなさまにとっては由々しき事態かと思います。
2017年 祝日の土曜日一覧
・建国記念日(2月11日)
・昭和の日(4月29日)
・秋分の日(9月23日)
・天皇誕生日(12月23日)
前年の2016年よりも4日も祝日が少なかったことがわかります。
祝日と土曜日が被るということは、「今月の3連休何しようかな」と考える楽しみが減ることでもあります。
実際に身体を休める日が少ないことはもちろんですが、3連休を待ち望むワクワク感が減るということは、日々一生懸命仕事に取り組んでいる方々にとって、精神的に大きな痛手なのではないでしょうか。
では、来る2018年はどうなのか…
2018年 祝日の土曜日一覧
・こどもの日(5月5日)
・山の日(8月11日)
・文化の日(11月3日)
な、なんと。
来年も今年に引き続き、3日も祝日と土曜日が被ります!
しかし、こちらの投稿をお読みいただいている方の中には、
「サービス業だから祝日なんて関係ないし」
「そもそも祝日は基本休みじゃないし」
という方もいらっしゃるかと思います。
平日・休日の過ごし方は十人十色です。
祝日が少ない、と嘆くのはやめて、何曜日であっても、いかに毎日を充実させるかを考えながら過ごしていくことが、彩りある毎日を送るうえで大切なことなのかもしれません。
日々の生活を送る中で発生するトラブル、家庭の問題、事故など、自分では対処しきれない問題が発生したときは、当事務所まで足を運んでいただけたらと思います。
年の瀬の空気が漂う一新総合法律事務所ですが、来る2018年を気持ちよく迎えられるよう、残り少ない2017年も、弁護士・事務員一同、頑張ってまいります。
【投稿:崎】
月間アーカイブ
- 2023年8月(1)
- 2023年2月(1)
- 2022年10月(1)
- 2022年8月(1)
- 2022年2月(1)
- 2022年1月(1)
- 2021年11月(1)
- 2021年8月(2)
- 2021年6月(1)
- 2021年5月(1)
- 2021年3月(2)
- 2021年2月(1)
- 2020年9月(1)
- 2020年8月(1)
- 2020年6月(3)
- 2020年4月(1)
- 2020年3月(1)
- 2019年11月(1)
- 2019年10月(2)
- 2019年9月(1)
- 2019年8月(1)
- 2019年7月(2)
- 2019年6月(2)
- 2019年5月(3)
- 2019年4月(2)
- 2019年3月(2)
- 2019年2月(3)
- 2019年1月(4)
- 2018年12月(7)
- 2018年11月(9)
- 2018年10月(1)
- 2018年9月(3)
- 2018年8月(2)
- 2018年7月(3)
- 2018年6月(2)
- 2018年5月(1)
- 2018年4月(3)
- 2018年3月(2)
- 2018年2月(2)
- 2018年1月(3)
- 2017年12月(4)
- 2017年11月(3)
- 2017年10月(3)
- 2017年9月(4)
- 2017年8月(3)
- 2017年7月(3)
- 2017年6月(2)
- 2017年5月(3)
- 2017年4月(10)
- 2017年3月(5)
- 2017年2月(2)
- 2017年1月(2)
- 2016年12月(3)
- 2016年11月(3)
- 2016年10月(2)
- 2016年9月(3)
- 2016年8月(5)
- 2016年7月(2)
- 2016年6月(2)
- 2016年5月(2)
- 2016年4月(4)
- 2016年3月(2)
- 2016年2月(2)
- 2016年1月(2)
- 2015年12月(3)
- 2015年11月(2)
- 2015年10月(2)
- 2015年9月(2)
- 2015年8月(2)
- 2015年7月(2)
- 2015年6月(2)
- 2015年5月(3)
- 2015年4月(3)
- 2015年3月(1)
- 2015年2月(2)
- 2015年1月(2)
- 2014年12月(5)
- 2014年11月(6)
- 2014年10月(5)
- 2014年9月(4)
- 2014年8月(5)
- 2014年7月(4)
- 2014年6月(4)
- 2014年5月(5)
- 2014年4月(4)
- 2014年3月(4)
- 2014年2月(4)
- 2014年1月(3)
- 2013年12月(4)
- 2013年11月(5)
- 2013年10月(5)
- 2013年9月(4)
- 2013年8月(5)
- 2013年7月(4)
- 2013年6月(4)
- 2013年5月(5)
- 2013年4月(5)
- 2013年3月(5)
- 2013年2月(4)
- 2013年1月(3)
- 2012年12月(5)
- 2012年11月(5)
- 2012年10月(4)
- 2012年9月(4)
- 2012年8月(5)
- 2012年7月(4)
- 2012年6月(5)
- 2012年5月(4)
- 2012年4月(6)
- 2012年3月(3)